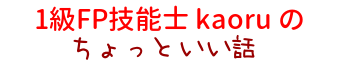投資では年代に応じて資産配分を見直すのが良いと言われています。
「若い時は株式を中心とした運用」「50歳になれば安全性が高い債券を中心」といった話を耳にしたこともあると思います。
最近では、このような調整を自動的に行う“ターゲットイヤーファンド”といった商品も注目されています。
最初は株式を中心の運用を行い、運用期間の経過にしたがって安定性が高い債券の比率を引き上げていく投資信託(自動調整)です。
説明を聞くと非常に合理的なイメージがありますが、相談業務を実践しているFPでこの投信を良いと思っている考えている人は少数派だと思います。
今回は年齢に応じた資産配分に関して、相談現場の経験をもとに書いていきます。
この記事の目次
常識を疑え!年代別の資産配分データはいつのもの?
資産配分に関しては、若いうちは株式が中心でリタイヤが見えてくる50~60歳になれば債券を中心にするという考えがあります。
資産運用の情報サイトや書籍などでも、見かけることがあります。
ただし、冷静に考えればこれが非常に古い考えに基づいていることが分かると思います。
60歳を運用の終着点にして、残り40年間を安心して暮らせるでしょうか?
 私は社会福祉士やFPとして年配の方とも接してきましたが、65歳を過ぎてもバリバリ働いてるというのは当たり前の光景。
私は社会福祉士やFPとして年配の方とも接してきましたが、65歳を過ぎてもバリバリ働いてるというのは当たり前の光景。
70歳でも日々アクティブに行動しているのも普通のことです。
収入がある期間や資産に余裕があるうちは、神経質にならずに従来からの投資配分で継続することに問題はありません。
年齢による資産配分の考え方に関しては人それぞれですが、今回は私が実践している方法を書いて行きます。
関連:年金支給が70歳になる?40代は凍りつくような現実を直視せよ
資産配分は株式と債券を半分ずつを基本としています。

私の投資については株式と債券を50:50で持つことにしています。
ただし、かなり大雑把で厳密に行っているわけではありません。
この二つの資産は理論上は値動きが反対になるので、 分散効果が期待できます。
ちなみに、年齢に応じて配分を変更するようなことはしません。
株式や債券の値動きはマーケットが握っているので、年齢に応じた最適な配分という考え方に無理があると考えているからです。
時期によって株式が強い時もあれば、債券が主役になることもあります。
私がターゲットイヤー型のファンドを利用しない理由は、最重要であるマーケットの動きを無視して資産配分だけを変更していくからです。
このタイプの投信に対しては懐疑的に見ているのが本音です。
年齢に応じてリスクを減らしたい場合はどうする?
ある程度の年齢に達したらリスクを減らしていきたいと考えてる人もいると思います。
その結果として債券比率を高めるという話が出てくるのですが、相談現場でこれを実践するケースはありません。
その理由はとても簡単で、リスクを減らしたければ一定額を売却して現金比率を高めればいいだけだからです。
 また、 積立投資をしていく中でも月3万円の積立を実施していたものを月2万円に変更して1万円は預金していくケースもあります。
また、 積立投資をしていく中でも月3万円の積立を実施していたものを月2万円に変更して1万円は預金していくケースもあります。
つまり、株式を減らして・・債券を増やして・・・、こんなややこしいことをする必要性はないということです。
目的は安全性が高い資産を増やす事ですから、現金の比率をあげるのが簡単な方法になります。
日本では資産運用という考え方がなかったので、教科書通りにやろうとする傾向があるのですが、その内容が古すぎて時代に合ってないケースが多々あります。
資産運用はシンプルで非常に簡単!
悩んでしまう時は、自分自身で難しくしている事がほとんどです。
あまり細かいことは考えずに、気楽に実施してみてください。
今回は「年代別の資産配分は時代遅れって本当?投資は70歳でも強気でOK」について書きました。
資産運用を行う上でヒントになる点があれば参考にしてみてください。
クレカ積立はマネックス証券!還元率1.1%(主要ネット証券で最大)

私の 運用方針 は【長期・分散・積立】が基本スタイルです。
そして、積立投資で活用しているのがクレカ積立!
積立の決済に対してポイントが付与されるのが魅力です。
このサービスで注目は マネックス証券![]() 。
。
マネックスカードで決済すれば、投信つみたての還元率1.1%!
主要ネット証券でNO.1の水準です。
毎月5万円の積立した場合、年間で6,600円分のポイントが貰える計算になります。
仮に20年間の積立投資を継続すれば、累計13万円以上のポイントが貯まることになります。
どうせ積立投資をするならば、利用した方がお得ですね。

※マネックスカードは、証券口座のオンライン上で申込する方式。
※カード積立を希望する人は、最初に口座開設を行ってください。
★マネックス証券は米国株投資でもメリットが大きい
米国株で時間外取引が可能な貴重な証券会社!
また、逆指値(リスクヘッジ)をしながら上値を追う戦略は私の鉄板手法です。