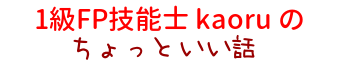FP(ファイナンシャル・プランナー)の仕事をしていきたいと考えている人やFP資格に興味を持っている人に向けての記事です。
当初は単発記事で終わらせる予定でしたが、継続要望が多いので月に1回くらいは書くようにしています。
今回は「小規模企業共済」について書いていきます。
将来の備えとして注目の制度に、個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。
掛金の全額が所得控除になることに加えて、運用益は非課税という大盤振る舞いですから利用しない手はありませんね。
ただし、これはあくまでも会社員などに対しての話。
FP相談では、個人事業主や小さな会社の役員といった人も多いです。
その場合は必ずしも『iDeCo』が最優先とは限りませんので注意してください。
個人事業主に対しては『iDeCo』よりも先に『小規模企業共済』について説明する方が喜ばれると思います。
この共済は”自営業者や小さい会社の社長の退職金”なんて呼ばれていますが、 加入対象者が一部に限られていることから知らない人も多いです。
FP を目指す人は、“どうしてiDeCoよりも先に提案する必要性があるのか?”という点に注目してみてください。
この記事の目次
小規模企業共済で節税しながら退職金・年金を準備する。
この共済は 「個人事業主」や「小規模な会社の役員」を対象としていて、廃業や退職などで仕事をやめたあとの資金を事前に積立しておく制度です。
預金しながら節税ができるイメージですね。
税制優遇はiDeCoと似ていて代表的な点は以下の2つです。
●受取りは「一括」ならば退職所得控除が利用可能。
掛金については以下
●掛金の金額変更は途中でも可能!年払いにも対応。
ちなみに、現在の予定利率は1%ですので銀行預金と比べると非常に高いですね。これに掛金の所得控除がプラスされますから非常に有利。
尚、受取金額は請求事由により差があります。共済の細かい内容についてはは小規模企業共済のホームページを確認してください。
税制優遇だけ見るとiDeCoと似ているので、小規模企業共済でなくてもいいような気がしますが、経営する上でのプラスメリットがありますので次に紹介します。
ココが凄い:途中解約が可能、 貸付制度がある

事業を行っていると、想定外の資金が必要になるケースがあります。
こういった時にiDeCoは原則として60歳まで引き出しができませんので 、資金としては期待できません。
しかし、小規模企業共済の場合は貸付制度があり納付済み金額の7割~9割の範囲内で 事業資金等の貸付が受けられます。
利率は内容により変わりますが、最高でも1.5%ですから好条件。
また、元本割れリスクはありますが60歳未満の段階で任意解約を行うことも可能。
※最終手段なので、なるべくなら貸付で乗り切りたい。
小規模企業共済の場合はiDeCoと違って年齢制限がないのも魅力。
働いている間はずっと継続できますし、加入についても60歳以上でもOKです。
小規模企業共済であれば、節税&退職金の準備をしながら事業の資金対策もできます。
経営者に話をするとiDeCoよりも共済を優先する人が多いですね。
尚、iDeCoと小規模企業共済は併用可能。
両方とも満額まで実施しすれば所得控除が年間に100万円以上ですので、個人としての節税効果は大きいですね。
検討は早く:事業が大きくなっても継続できる
小規模企業共済をiDeCoよりも優先的に紹介したい理由は、貸付制度のメリット以外にもう一つ重要な点があります。
この共済は個人事業主や小さい会社の役員など加入要件が限定されています。
そして、加入後に事業が大きくなったとしても、原則として強制解約させられるようなことはありません。
一方で事業が大きくなってからでは加入することができません。
つまり、共済の加入は早い段階で検討しておく必要があります。
尚、 小規模企業共済の加入要件については以下のようになっています。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
iDeCoについては後から検討でも構わないのですが、小規模企業共済に限っては加入資格があるので 、その点についてはシッカリ説明しておいてください。
尚、 私自身も独立した時から小規模企業共済に加入しています。
FPへのニーズは大きい!成功は本人の努力次第

今回は「FP業務の実践!個人経営者にはiDeCoより小規模企業共済の魅力を伝えよう」について書きました。
将来の資金準備としてはiDeCoが最有力というのが一般的な考えですが、その人の立場によっては優先順位が変わる点は憶えておいてください。
さて、少し前に金融庁が「老後資金に2000万円が必要」という発信がありました。
内容の賛否は別として老後資金に対して意識が高まったことからFPへのニーズも高まっていくと想像しています。
また、 FP業だけで10年、20年としっかり生計を立てている人もいます。
近年は知名度が上昇しており、“FP”という言葉のチカラが日々高まっている事を実感しています。
仕事をしている私からすると「信頼・信用」が得られるFP資格は強烈なアドバンテージ。
また、個人的な経験ですが資格試験は年数経過するにしたがって難易度があがっていくことがあります(宅建など)。
FPに興味がある人は積極的にチャレンジしてみてください。
自己投資:ファイナンシャル・プランナー資格
「お金に関する知識や判断力をつけたい人」「FP業務に関心がある人」は、FP資格を目指してみてください。
2級FP技能士 からは名刺に記載するなど、仕事への好影響も期待できます。
人生100年時代!今後の有望資格だと思います。
生活でもお金の知識を持っておくことは重要!
尚、資格がなくてもFP業務はできますが、ある・なし では信用度は全然違います。
FP技能士は国家資格と言う点も魅力!
更新も無いので、一生資格になります。
興味がある人は是非チャレンジしてみてください。
![]()
ユーキャンファイナンシャルプランナー(FP)講座![]()
2級FP技能士 試験時期【1月/5月/9月】
![]()
講座の課題等に合格することで『2級技能検定』の受験資格が得られます。
※通常は『実務経験2年以上』『3級資格の取得者』といった要件あり。