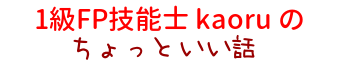資産運用で投資信託を利用する時には、コストが安い商品を選ぶのが基本。
保有期間中のコストである【信託報酬】は1%違えば、長期運用だと結果に大きな違いとなって表れるので注意が必要です。
100万円を5%の利回りで運用した場合
| 信託報酬 | 運用10年 | 運用20年 | 運用30年 |
| 0.5% | 155万 | 241万 | 374万 |
| 1.0% | 148万 | 219万 | 324万 |
| 1.5% | 141万 | 199万 | 280万 |
長期運用では1%の違いで100万の差になることもあります。
値動きが指数に連動するインデックスファンドを選択する場合は、できる限りコストが安い商品から選択する方が有利と言えますね。
昨今はコストを強く意識する投資家が増えてきた為に、運用会社のコスト競争も激化!
半年も経過すると低コストランキングの顔ぶれがガラリと変わっていることもあります。
運用している立場としては、低コストファンドが増えるのは嬉しいのですね。
ただし、低コストに注目しすぎて保有商品をココロコロ変更するのも考えもの!
軽い気持ちでファンドの乗換えた結果、資産形成にブレーキが掛っているケースも少なくありません。
今回は現在保有している投信を売却して、新しいファンドを購入する時の注意点について書いていきます。
この記事の目次
投資信託の変更は、儲かっている時こそ慎重に!
投資信託はコストが安いのを選ぶのは良い事です。
ただし、これが無条件で適用されるのは“初めて資産運用を実施する時”の話。
既に投資信託を運用していて利益が出てる時は注意が必要です。
売却時には原則として利益の20%が税金で差し引かれるので、 新しい投資信託に乗換えることで運用資金が目減りしてしまいます。
この状況(利益100万円)で売却すると税金が約20万円が差し引かれるので、手元に残るのは約280万円になる。
上記の状態で低コスト投資信託に乗換えした場合は、以前よりも約20万円が目減りした状態でスタートとなります。
 これは机上の計算で言えば、販売手数料が6~7%も取られる事と同じ効果!
これは机上の計算で言えば、販売手数料が6~7%も取られる事と同じ効果!
良かれと思って低コスト投信に乗換えたのに、資産形成にマイナスになってしまうパターンです。
“こんな失敗をする人はいるの?”と思うかもしれませんが、インデックスファンドの乗換えで非常に多いミスの1つです。
逆に含み損を抱えている場合は売却しても税金は発生しませんので、売却して信託報酬が安いファンドに乗換えた方が有利。
ただし、損失が出ている中での売却というのは心理的な抵抗が大きいので、頭で分かっていても実行に移せるのは一部の人にに限られています。
投信の乗換えでは“利益確保をしたい心理”を吹き飛ばせ!

投資信託300万円(元本200万円+含み益100万円)を売却すると約20万円の税金が差し引かれて280万円になると書きました。
このような方法で投信を乗換えるのは非効率なのですが、税金分は長期保有することで少しずつ埋めること可能です。
ただし、私の経験で言えば、多いのは次のパターンです。
個人投資家で目立つのは、利益部分だけは現金化して最初の投資元本(200万円)だけを新しいファンド購入する方法です。
この手法は、複利効果は期待できなくなりますので資産運用としては0からの再スタートと同じです。
 つまり、商品選択は最安コストで良いのに資産がなかなか増えない。
つまり、商品選択は最安コストで良いのに資産がなかなか増えない。
それどころか、手数料が遥かに高い投資信託で運用している人よりも最終結果(資産額)が悪くなるというパターンも・・。
例えば、お金持ちの人に利用者が多い『ラップ口座』と呼ばれる専門家に運用を丸投げする方法があります。
おそらく、資産運用に関する本をみれば“ラップ口座はコストが高いのでNG”と書いてあるはずです?
私も全く同じ意見なのですが、ラップ口座のようにコストが高いサービスを利用しているのに資産がシッカリと増えている人は多いです。
この理由は凄く簡単で、運用を長期継続しているからです。
高コストで運用効率は下がっても、全額投資を継続しているので複利効果で資産が増えていくのです。
利益が出るたびに現金化していては、毎月分配型の投信と変わりません。
補足:やっぱり長期保有が有利?共通KPIの結果
2019年6月末に金融庁が「共通KPI」を発表しました。
これは、投信を販売する金融機関を評価する上で非常に参考になります。
19年3月末で運用損益がプラス(含み益)の顧客割合が明らかになったのですが、その中で97%という圧倒的な数字を出したのが【セゾン投信】です。
大手ネット証券が75%程度という事を考えると、97%という数字は凄いですね。
この結果の理由としては、セゾン投信は“長期投資”を看板にしているので長期投資家が大多数という背景がある為だと思われます。
魅力的な投資信託が出てきたらどうしたらいいの?

市場に連動するインデックスファンドに投資をする場合は、最安コストの商品を選ぶのが効率的。
積立投資をしていて気になるのは、現在保有中のインデックスファンドより低コストの商品が出てきた時ですね。
含み損が抱えていれば単純に売却して乗り換えるだけですが、多くの場合は含み益がある状態だと思います。
私自身のパターンで言えば、今までの積立投信については一旦ストップしてそのまま保有(売却しません)。
そして次回の積立からは、 新たな低コストファンドに変更して継続する方法で行っています。
米国市場への投信積立としては、現在「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」で実施していますが、以前は別の投資信託でした。
★私の積立投信の変化(米国株)
初:iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド:信託報酬0.45%
次:iFree S&P500インデックス:信託報酬0.243%
今:eMAXIS Slim米国株式(S&P500):信託報酬0.162%
※信託報酬は2019年9月30日現在
途中で商品は変更していますが、積立を中止しただけで【iシェアーズ~】【iFree~】とも保有したままです。
売却して再投資は面倒なので、積立の対象商品だけを変更するようにしています。
ズボラ投資家は注目!eMAXIS Slimシリーズ
米国市場に連動する投資信託では、新たに発売された『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』が信託報酬が最安(0.09264%)になっています。
現状ではSBI証券のみの販売となっています。
関連:SBI証券で投資信託を買う人が多い理由!人気の秘密は5つの最高レベル
この状況で私が「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」での積立を一旦停止して上記の商品に変更するかといえば、その答えは『NO』です。
その理由として eMAXIS Slimシリーズは、コストに対して「業界最低水準を目指し続ける」という方針になっているからです。
過去のケースでは最安ファンドが出てくるたびに、eMAXIS Slimが引き下げを実施して追随していますから今回も同じパターンになると予想しています。
 私がこのeMAXIS Slimを選んだ理由は、「最低コストのファンドは何?」みたいな事を考えるのが面倒だからです。
私がこのeMAXIS Slimを選んだ理由は、「最低コストのファンドは何?」みたいな事を考えるのが面倒だからです。
積立投資は定期的かつ継続的に一定額の金融商品を購入する投資手法なのでタイミングなどを考えなくて良いのがメリット!
最安コスト商品が出るたびに反応していては、ホッタラカシ投資の意味がありませんからね。
「業界最低水準を目指し続ける方針」の eMAXIS Slimシリーズは、私のようにズボラ投資を行いたい人にはピッタリだと思います。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」などが人気です。
今回は『積立投資の盲点!途中で投資信託を変更するのは予想以上に難しい』について書きました。
資産運用をするにあたりヒントになる点があれば、参考にしてみてください。
尚、最後に紹介したeMAXIS Slimシリーズに関しては大手ネット証券であれば、だいたい取扱っています。(以下の5証券に関しては確認済み)