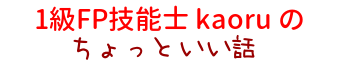足元の相場は少し揺れていますが、年初から比較すると資産が大きく増えています。
ただし、海外資産がドル高により嵩上げされている影響が大きいですね。
米国株を見ると、ドルベースではNYダウが年初来リターンがマイナスになっています。
※23年10月3日現在。
少し前までは、ChatGPTのような生成系AIシステムに対する関心が爆発的に高まっていて、IT関連株の上昇が凄かったのですが・・・。
しかし、こういった話題銘柄についても勢いが消失。
ナスダック指数(成長株)は数字上は好調に見えるのですが、過去2年の高値に届いていないのが実態です。
株式市場は右肩上がりが当たり前の雰囲気がありますが、これは「近年がそうだった」だけの話。
今回は株式市場の不安要素と運用姿勢について書いていきます。
※個人的な投資についての記事で推奨ではありません。
※投資判断はご自身で行ってください。
この記事の目次
長期的にはドル安円高基調を想定(海外資産の評価下落)
現在の資産運用で大きなアドバンテージになっているのが ドル高円安 です。
足元を見ると、ドル円は150円前後ですね。
9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、将来の利下げ従来よりもペースダウンする予想となりました。
政策金利見通しは、24年は5.1%、25年は3.9%となっています。
市場は金利の高止まりを警戒から、ドル高となりました。
ただし、ドル高は今期に限った短い視点で考えた方が無難!
米政策金利の見通しては 26年には2.9%、中長期的には2.5% です。
時間経過で利下げが進む予想については変わっていません。
一方で日銀の金融政策の変更時期について、24年4月ごろを予想するエコノミストが増えてきました。
この時期が正しいかは別として、円金利については遅かれ早かれ上昇していくと考えるのが自然です。
為替の嵩上げ分は、割り引いて見ておいた方がいいかな?
仮に1ドル120円ならば、資産は20%目減りします。
中長期見通しでは、米金利↓・円金利↑ となるので、金利差縮小でドル安・円高となる公算が高いですね。
FRBの政策金利の中長期見通しをもとに考えると、最終的に1ドル120円くらいを予想しています。
短期間で決済を考えている人ならば直近の為替に注目ですが、この記事を読んでいる人の多くは長期投資が多いと思います。
長期視点では、現状の為替が一時的である可能性をシッカリと頭に入れておきたいですね。
米国経済は減速予想、中国経済も復活には時間が掛りそう
為替についてネガティブな見方を書きましたが、株価がそれ以上に上昇すれば問題ありません。
実際にこれまでは、株価上昇パワーが為替変動を打ち消してきました。
この株価上昇のカギを握るのが、米国・中国の2大経済大国の状況です。
先ず米国経済ですが、年初からの予想に反して景気が非常に強いです。
この理由は、インフレでも個人消費の意欲が衰えなかったことが要因だと考えています。
ただし、強い消費が今後も続くかにつては疑問があります。
コロナ禍に積み上がった過剰貯蓄は、取崩しによりまもなく消失すると予想されています。
さらに、今月からはコロナ禍で免除になっていた学生ローンの支払いも再開。
物価上昇が続く中で、個人消費への逆風が高まってきました。
米GDPの成長率予想から考えても、来年以降の米経済の先行きが明るいようには見えません。
米国同様に株式市場に大きな影響力があるのが中国です。
仮に米国が失速しても中国経済が強ければ、見通しが明るくなります。
不動産市況の悪化で経済が停滞しいてる状況を受けて、直近では景気対策を次々と発表しています。
ただし、大きな改善が見込まれるような対策が無いので、市場に与えるインパクトは小さいのが実情。
さらに、生産年齢人口は減少へと向かっており以前ような爆発的な成長が見込みずらくなってきました。
中国経済が完全に上向くまでには時間が掛ると考えています。
長期目線でジックリと投資をする!足元の良し悪しは気にしない
ザッと足元の状況を書いてみましたが、ネガティブな内容が多いですね。
足元で株価が下がっても「買いチャンス」とは簡単に言える状況ではありません。
今回の記事を読んで不安になってしまった人もいるかもしれません。
ただし、これは足元から当面の見通しであって、5年後や10年後を予想した話ではありません。
例えば、米国株水準は過去と比較すると割高です。
ただし、利益成長が進めば時間経過で割高感は解消されます。
現在の株式市場にマイナス材料が多くても、それが永久的に続くとは想像しずらいですね。
私は1年くらい株式市場が低迷することも考えていますが、その後は再び上昇軌道を描いていくと予想しています。
株式市場が良い時期と悪い時期があるのは当たり前の話。
最近は月ごとに投資の見通しや予想がコロコロ変わっています。
ただし、これらは全て短期的な話です。
ブログを書き始めて10年以上になりますが、10年単位の長期的な経済見通しについて右肩上がりで変わっていません。
この事からも、一喜一憂せずに淡々と積立投資を継続していくのが堅い戦略だと考えています。
今回は「世界の経済大国である米中に不安あり!株式投資はジックリと行う」について書きました。
記事の中で参考になる点があれば運用のヒントにしてみてください。
【楽天証券】クレジットカード&楽天キャッシュで積立投資

楽天証券は新NISA制度において、楽天証券は投資信託・国内株式・米国株式・海外ETFの取引手数料が無料することを発表しました。
また、楽天カード決済(上限10万円)・楽天キャッシュ決済(上限5万円)で積立を行えば、楽天ポイントが貯まります。
楽天カードと楽天キャッシュの積立は併用可能!
最高毎月15万円のキャッシュレス積立ができるのは楽天証券だけ。
さらに、国内株式(現物/信用)取引手数料が0円になる”ゼロコース”をスタート。
※手数料コースを「ゼロコース」に変更することで適用。
新NISAは勿論ですが、投資信託の積立や国内株式の取引を行う人には注目の証券会社です。