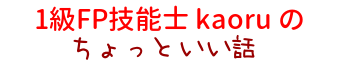今年に入ってから株式は好調ですが、私はこの流れに乗れていません。
積立投資の増額はしましたが、個別株の投資はIPOくらい・・。
一方で、積極的にスポット買付している資産があります。
不動産投資信託のJ-REITです。
もっとも、J-REITが好調かと言えば、そんなことはありません。
他の資産と比較してもリターンが大きく見劣りしており、絶不調と言ってよい状況です。
直近1年の状況を見れば、株式投資との差は歴然です。
(基準:23年8月2日)
| 資産クラス | 1年リターン | 年初来リターン |
| 日経平均株価 | 20.6% | 25.3% |
| S&P500 | 12.2% | 17.6% |
| 東証リート指数 | -3.9% | -1.6% |
完全に、東証REIT指数(リート全体)は独り負けです。
1年・年初来の両方でマイナス・・。
先月と比べても株式との差が拡大しました。
金利上昇や都内オフィスビルの空室率増加で不透明感が漂っており、多くの投資家が距離を置いている状態です。
しかし、見方を変えれば、割安で放置されているとも言えます。
回復までには時間が掛かると思いますが、長期視点で積極的に投資を実施しています。
先ず第一弾で、今年の3月末に約700万円を買付。
この時はETFを中心に買付しました。
続く第2弾は、6月に750万円を投資。
物流特化型リートの公募増資にタイミングで買付。
そして、今回は第3弾!
7月に500万円の追加投資を実行しました。
今回はJ-REITへの投資について書いていきます。
※個人的な投資についての記事で推奨ではありません。
※投資判断はご自身で行ってください。
この記事の目次
Jリートへの投資を継続!価格と業績のギャップあり
投資の格言に【落ちてくるナイフはつかむな】という言葉があります。
これは、下落している時は手を出さず、底打ちを確認してから投資すべきという意味。
過去に逆張りで失敗した経験がある私にとっては、耳が痛い格言です。
J-REITは約2年にわたって低迷を続けています。
株式市場は熱狂的に盛り上がっていますが、リートは蚊帳の外ですね。
底値もハッキリしないので、本来であれば上昇を転換を確認してから投資対象と言えます。
金融政策(金利動向)とオフィス空室率の上昇!
この2つがJ-REITの重しになっています。
今回は浮上を確認する前の投資なので、事実上の逆張り!
株式投資であれば、悪い見本となります。
実際に7月末に日銀は大規模緩和策を事実上「修正」のニュースが発表された際には、一時的にJ-REITは売られました。
ただし、J-REITは賃料収入がメインなので、将来の収益は強固安定です。
インカムゲインの視点にたつと、非常に魅力的な投資対象ですね。
また、金利上昇についても、リートは長期固定金利での資金調達が大半なので影響は限定的というのが真実です。
懸念材料が表面化しても、配当(分配金)については従来通り維持されると考えています。
J-REIT投資については安定的に配当収益を得ることが最大の目的。
低迷する株価(投資口価格)に対しては、仕込み時期と割り切って買付しています。
次の項目では、23年7月に追加投資をしたJ-REITについて書いていきます。
物流特化型のGLP投資法人に約500万円を投資!
今回の投資は物流特化型REITのGLP投資法人(3281)。
7月に5回にわけて40口を購入しました。
平均買付単価は1口約14万円。
残念ながら8月に入っても下落が続き足元は 含み損 です。
下落トレンドが継続中なので、まだまだ下がる可能性がありますね。
私の場合は、買付から数か月くらいマイナス(含み損)になるのはいつものこと。
「また、このパターン・・」という感じです。
もっとも、短期で儲けるチカラが無いから長期投資を実践しています。
インカムゲインに着目した投資ですから、株価変動に一喜一憂しても仕方ありませんね。
次の株価(投資口価格)確認は年末になるので、その時にプラスになっていることを期待しています。
尚、この銘柄を買付した理由は、安定収益が期待できる物流特化型であること。
更に価格が大幅に下がっていたことがあります。
GLP法人は2021年末に保有物件の「GLP舞洲II」が放火による火災に見舞われました。
建物滅失の損害は火災保険があるのですが、修繕工事を施しても倉庫としての継続的な使用が困難な状況によりテナントとの賃貸契約が終了。
この頃から株価(投資口価格)がズルズルと下がり続けて現在に至ります。
ちょっと底が見えずらい状態ですね。
ただし、スポンサーのGLPグループは日本において賃貸用物流施設運営事業者としては最大規模を誇ります。
優先的な物件取得やテナント獲得力(リーシング力)に強みがあるので、長期の安定成長が期待できると考えています。
分配金についても、再び上昇へと向かうと予想しています。
7月に100万円×5回の投資。
株価は低迷中ですが、長期視点でホールドします。
GLP投資法人(3281)の利回りは3%後半~4%です。
J-REIT全体でみると、かなり低めの水準。
これは格付AAと、物流施設で国内最大級の信用度に対する裏返しでもあります。
私は20年以上の長期保有を前提にしているので、利回りよりも継続性や増配余地を重視しています。
今回の500万円買付で年間20万円弱の配当金(分配金)が確保できました。
安定収入が増えると日々の生活に安心感が生まれますね。
直近の半年間で、J-REITに2000万円を投資!
J-REITへの投資拡大により、私の資産は株式の市場平均リターンよりも劣後する可能性があります。
しかし、年間の配当収入は大きく増加しました。
私にとっては目先のリターンよりも、定期的に予想できる金額が増えることの方が重要。
この投資で、10年以上続く安定収入を確保できたと考えています。
さて、今年に入ってJ-REITへの投資は約2000万円以上。
年間で約80万円の配当金(分配金)を獲得!
月間だと6万5千円強のプラスになります。
これが 来年・再来年・10年先へと続くと考えると、とても嬉しいですね。
私が目指すのは長期的な収益源の確保。
足元(短期)で【勝った・負けた】みたいな話は、あまり興味がありません。
5年後・10年後に『あの時に買付けしておいて良かった』と思えるような結果を目指して、これからも投資をしていきたいと思います。
今回は「Jリートに500万円を追加投資!いきなりマイナスの含み損です」について書きました。
記事の中で参考になる点があれば運用のヒントにしてみてください。
尚、J-REITについては、新NISA(成長枠)の投資対象としても注目です。
非課税期間が無期限になるので、配当金(分配金)は将来の不労所得として非常に魅力的だと考えています。
私がSMBC日興証券をメインにしている理由
現在、個人投資家の証券口座は 楽天証券 と SBI証券 に集中しています。
私もこられの証券口座を保有していますが、現在のメインは SMBC日興証券 です。
SMBC日興証券をメインにする理由は?
②個別株(ETF・J-REIT含む)でドルコスト平均法が可能
③投信積立の買付手数料が無料!米国株の取扱いあり
④大手証券なので魅力的な新発債の販売が期待できる
詳しい内容は コチラの記事 で紹介しています。
(ネット証券を圧倒する5つの魅力)
私は配当を貰いながら分散投資が可能なETF(高配当)を重視。
SMBC日興証券は、ETFの金額買付(キンカブ)やETF積立(キンカブ定期定額売買)が可能な貴重な存在。
【分散・長期・積立】に【配当(分配金)】を加えたい人は、SMBC日興証券は有力な選択肢だと思います。
公式 SMBC日興証券![]()