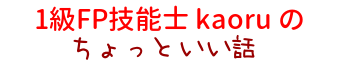2020年3月は新型コロナウイルスへの警戒から世界中の株式が大きく下落しました。
しかし、その後は下がりすぎた反動による買い戻し!
主要国が一斉に大規模な金融緩和に踏み切ったことで、大幅上昇になりました。
個人投資家からは、『前月比で持ち株が△%上昇した』『資産が前月から〇百万も増えた』といった明るい話も聞こえてきます。
一方でFPの視点で見た時に、非常に気になる点があります。
それが“資産全体が増えていないケースが目立つ”ことです。
ちょっと不思議ですね?
今回は資産が増えずらい人に多い『資産運用の勘違い』について説明します。
この記事の目次
“前月から〇%上昇した”は営業トークの定番です。
『保有株が2か月で30%上昇しました』
こんな言葉を聞いたら、その人の投資手法が気になっちゃいますよね。
「自分も・・」なんて想像してしまうのが普通です。
30%上昇なんてあり得ない話にも感じますが、これは直近で発生した事実。
 NYダウは2020年3月23日終値は18591ドル、その約2ヶ月後の5月末終値は25408ドルです。
NYダウは2020年3月23日終値は18591ドル、その約2ヶ月後の5月末終値は25408ドルです。
これは上昇率にすると約+37%という強烈な数字です。
しかし、NYダウは2月12日終値が29551ドルの最高値をつけていますから、それと比較すれば反発したとはいえ4000ドルも低い水準。
こういった時は注意してください。
結論を言うと、数字のマジックを使って簡単に初心者を惑わすことができます。
30%下落後に40%上昇しても、元の水準には回復しません。

金融機関で「○○ショックでA投信は30%下落しましたが、たった1ヶ月で40%も反発しました」と説明を受けたらどう思いますか?
経験の浅い人ならば、『短期間でプラスに転じて凄いなぁ~』と興味を持つかもしれませんね。
しかし、実際に計算すると、これは元の水準に戻っていません。
例えば100万円が30%減少すれば70万円になりますね。
この70万円を1.4倍すると(40%上昇)、その答えは98万円です。
でも、以下にような表を見せられたら、資産が増えそうに感じてしまう人も多いはずです。
★A投信の10年間
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
| -30% | +40% | -30% | +40% | -30% | +40% | -30% | +40% | -30% | +40% |
ちなみに、上記の表どおりに変化していけば、100万円の資産は10年後には90万円に目減りしてしまいます。
つまり、価格が大きく下がると回復には相当なパワーが必要だという事です。
私が徹底的に保守的な運用を継続しているのは、これが大きな理由です。
例えば以下のような値幅が小さい商品を考えてみましょう。
★B投信の10年間
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
| -2% | +5% | -2% | +5% | -2% | +5% | -2% | +5% | -2% | +5% |
この場合は10年後に115万円になります。
先ほどの商品と比べて魅力は小さく感じますが、実際には資産がシッカリ増えています。
直近の成績を確認する場合は、数字のマジックに騙されないように注意してください。
ちなみに、コロナショックではNYダウでは、この現象が起きています。

下落率と上昇率で同じ水準の地点を抜き取ったのですが、株価の変化をみると下落の数字が遥かに大きいことが分かります。
 つまり、前月から〇%上昇と言っている人の中には、年初来から見ると資産減少という人もいるという事。
つまり、前月から〇%上昇と言っている人の中には、年初来から見ると資産減少という人もいるという事。
前月比や短期的なデータで自分よりも上昇率が高い人がいても、気にする必要は全くありません。
上昇率が高いからっといって資産が増えているとは限らないのです。
周囲の事は気にしないで、自分ペースを維持することが大切です。
【補足】単純平均のリターンにも罠がある。
先ほどの-30%と+40%の10年間を繰り返すA投信は、単純に毎年の1年ごと上昇率を合計して10(年)で割れば、平均は+5%となります。
しかし、現実には10年間で資産が▲10%というのが実態です。
それに対して、-2%と+5%の10年間を繰り返すB投信は、毎年の上昇率を合計して10(年)で割れば、平均は1.5%でA投信よりも小さい数字。
数値は小さいのですが、10年間でシッカリとプラスが出ています。
先ほどの“単年ごとの上昇率の表”と“単純な合計平均”を出せば、A投信の方がB投信よりも良い成績だと勘違いさせることも可能という事です。
短年の成績ではなく、長期でどれくらい上昇したかをシッカリ確認する必要がありますね。
例えば、【セゾン資産形成の達人ファンド】は「R&Iファンド大賞」で投資信託で最優秀ファンド賞を6年連続で受賞しています。
しかし、単年でみると決して凄いリターンではありません。
先ほどのB投信のように、大負けせずにプラスを積み重ねているので長期だと資産が大きくなるのです。
大幅上昇なんて狙う必要なし!負けない運用を心掛ける

私が資産運用で心掛けていることは『大負けをしないこと』です。
これを継続していけば、勝手に資産は増えていくと思っています。
もちろん、このような堅い投資をしていけば他の人よりもパフォーマンスが低い年も多々あります。
実際の話として、私は2019年は利益こそ出ましたが、リターン率は平均を大きく下回りました。
一方でコロナショックが起きた今年も、昨年と同じペースで増やせています。
これは、大負けを防ぐために米国株で逆指値をしていたことが大きな要因です(2月に持ち株の大半が利益確定となりました)。
★私のメイン手法です。コロナショック後に再投資をした銘柄は、現在20%~30%の含み益が出ていますが、こちらも全て高値から8%下落したら自動売却の設定をしています。
今から急落があった場合でも15%程度は利益が残せるようにしているという事です。
今年からはJ-REITにも投資をしていますが、こちらもSMBC日興証券で一定水準の下落があると知らせてくれる機能を利用しています。
投資信託の積立についても、メインにしているものは値動きの小さいバランスファンド。
リスクを抑えた投資は強気に資金を投じられるので、結果的に資産アップの早道になると考えています。
この面白味ゼロの保守的な方法で相場にしがみついていた結果が、現在の資産につながっています。
⇒ 資産が1億円を突破!ガッカリ度120%のショボすぎる投資手法
これからも、地味だけど“負けない投資”を継続していきたいと思います。
今回は「株価の上昇率に騙されるな!低リスク投資が資産運用に向いている理由」について書きました。
記事の中でヒントになる点があれば、資産運用の参考にしてみてください。
【+α】投資の情報収集ってどうするの?

投資の情報について『調べる方法が分からない・・』という相談が多いです。
私は週に1回、「グローバルウィークリー」という情報を確認するのを習慣にしています。
これは、岡三証券で発行している情報誌ですが、岡三オンライン(岡三証券)の口座を持っているとWEBで無料で読む事できます。
「グローバル」「日本株式」「米国株」「債券」「為替」など各項目について、 直近の状況と今後の見通しがコンパクトにまとめられていてます 。
ユックリ読んでも20分程度!
私は週の頭にこれを読んでスタートします。
私の活用方法をまとめていますので、興味がある人は確認してみてください。
業界では“情報の岡三”と呼ばれるほどシッカリした会社。
(J-REIT各社の決算報告レポートもあります)
尚、IPO申込が口座0円でも可能という点も注目です。
公式 岡三オンライン 口座開設キャンペーン
(期間限定:口座開設+5万円の入金で2000円プレゼント)