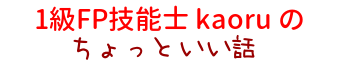近年は米国株に興味を持つ投資家が増えてきました。
アメリカ市場は100年以上も右肩上がりを続けているので当然だと思います。
資産運用としてはリスクを抑えるためにエリアの分散を推奨していますが、現実的には世界株式は米国市場の動きに連動する傾向があります。
世界45カ国の株式時価総額に占めるアメリカのシェアは約55%。
(2019年9月現在)
この状況から 「米国株だけに投資すれば良い」 と考える人も少なくありません。
実際に世界分散するよりも米国集中の方が好成績となっています。
参考までに世界株式(VT)と米国株(VOO)に連動する海外ETFに投資した場合の年率リターン(5年)を記載しておきます。※2019年10月末現在
| 商品名 | 投資対象 | リターン |
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 全世界株式 | 約7% |
| バンガード・S&P500ETF(VOO) | 米国優良株 | 約11% |
この結果をみれば米国株集中というのは魅力的な選択肢の一つであることは間違いありませんね。
ただし、米国株の強さが将来にわたって続くかといえば・・不安要素も?
今回は米国株に長期投資をするにあたってのリスクについて書いていきます。
この記事の目次
米国企業は強い!ただし、今後も不動の1位とは限らない
米国株が注目される最大の理由は、長期間にわたって右肩上がりで成長してきた実績があるからです。
私自身もこの強さに魅せられて、NYダウやS&P500に連動するETFには大きな資金を投じています。
ただし、ここで勘違いしてはいけないのは米国企業が常に絶対王者として君臨していたわけでは無い事です。
以下に1989年末と2019年8月の株式時価総額のトップ5を並べてみましたので確認してみてください。
★1989年末と2019年8月時点の時価総額TOP5
| 順位 | 1989年12月 |
| 1位 | NTT |
| 2位 | 日本興業銀行 |
| 3位 | 住友銀行 |
| 4位 | 第一勧業銀行 |
| 5位 | アイビーエム(IBM) |
| 順位 | 2019年8月 |
| 1位 | アップル(AAPL) |
| 2位 | アマゾン・ドットコム(AMZN) |
| 3位 | マイクロソフト(MSFT) |
| 4位 | アルファベット(GOOGL) |
| 5位 | バークシャー・ハサウェイ(BRK.B) |
1989年末は日経平均株価が4万円に迫った株バブルの時期ですが、この時は日本企業の強さが際立っていました。
トップ10のうち7社は日本企業ですから、米国株に投資なんて考える必要もありませんね。
 現在はというと(2019年)、米国IT企業が上位を独占しています。
現在はというと(2019年)、米国IT企業が上位を独占しています。
しかし、トップ10では2社が中国(アリババ・テンセント)、11位には韓国(サムスン電子)といったアジア企業があります。
つまり、米国企業が過去・現在・未来にわたって圧倒的トップと言える根拠は何もないのです。
また、米国企業の中でも競争が激しくトップ企業の入れ替えも頻繁ですので、個別株を永久保有というのも簡単な話ではありません。
財務体質が強固で時代に合った30銘柄に厳選されているのが魅力!
NYダウへの投資が魅力!
米国企業への脅威!新興国の猛追撃がはじまった

米国市場の状況を確認する上で重要インデックスがS&P500です。
大型株500社程度で構成されていて、時価総額ベースでは米国市場の80%を占めます。
産業ウェイトをみると、1位:IT関連、2位:金融、3位:ヘルスケアの順番。
前半で時価総額トップ5を書きましたが、そこもIT関連企業がズラリでしたね。
この分野で重要になるのが技術力となりますが、今後を占う材料の一つとなる「国際特許出願数」で2018年に大きな変化がありました。
それは、 アジアからの出願が5割を超えた ことです。
全体の1位は米国ですが、2位:中国は横並び状態で3位:日本も健闘しています。
出願数をザックリとエリアで分けると全体の半分がアジア、欧州と北米が各4分の1となっています。
ここで気になるのは、2018年は中国と日本は出願数が伸びているのですが、米国は微減となっている点です。
近年の米国は完全に横ばい状態となっており、アジア地区との勢いの差は鮮明。
日本の特許は車や電気といった製造業が中心ですが、中国は通信関係やAI分野といった米国の中心産業が多いので米国としても気になると思います。
こういった背景を頭にいれながら、各国の成長見通しを見ると面白いと思います。
参考までにIMFの世界経済見通しを記載しておきます。
| 2020年 | ※2021年 | ※2022年 | |
| 世界 | ▲3.1% | 5.9% | 4.9% |
| 先進国 | ▲4.5% | 5.2% | 4.5% |
| 米国 | ▲3.4% | 6.0% | 5.2% |
| ユーロ圏 | ▲6.3% | 5.0% | 4.3% |
| 日本 | ▲4.6% | 2.4% | 3.2% |
| 新興国 | ▲2.1% | 6.4% | 5.1% |
| 中国 | 2.3% | 8.0% | 5.6% |
| インド | ▲7.3% | 9.5% | 8.5% |
※2021年・2022年はIMF予想(2021年10月12日)
※前回7月より21年の世界経済見通しは0.1%の下方修正。
先進国の成長エンジンは米国であるのは間違いありませんが、世界全体の成長は新興国が握っているのが現実です。
もっともアメリカは基軸通貨(米ドル)を持っていますし、平均年齢が若く消費に積極的な国民性ですから今後10年程度は不動のトップだと予想しています。
ただし、20年・・30年・・と現在の影響力を世界にもてるかと言えば疑問です。
世界時価総額トップ5の企業から米国の名前が消えても何ら不思議ではありません。
資産運用では大儲けを狙う必要はない!狙うべきは確実性です。
今回は「米国株に集中投資することのリスク!世界分散が必要な理由とは?」について書きました。
現在の状況では、「米国株1本でもOK」といのが私の本音です。
効率的に資産を増やしたい人にとっては有力な選択肢だと思います。
ただし、私が投資で失敗した時の事を思い出すと、だいたいが「もっと儲けたい」と考えて欲張った時です。
「平均以上の成績を残したい・・」「あの人が成功しているのだから私も・・」という気持ちが冷静さを失わせたのだと思います。
私自身は長く投資をしている事もあり資産は1億円以上にまで膨らみました。
⇒ 資産が1億円を突破!ガッカリ度120%のショボすぎる投資手法
ただし、この資産アップに貢献した投資というのはガチガチの世界分散ファンドだったり、誰でも知っているような退屈な銘柄だったりします。
 資産を大きくしたいと考えたら、目先の小金をチョコチョコ稼いで積み重ねるよりも、失敗しないことを重視して長く運用する方が良いと思います。
資産を大きくしたいと考えたら、目先の小金をチョコチョコ稼いで積み重ねるよりも、失敗しないことを重視して長く運用する方が良いと思います。
私が投資でミスをした時は、こんな反省をするようにしています。
「最初の頃は、預金よりも増えればいいと思っていたのでは?」
この考えを維持していていれば、投資は損する方が難しいと思います。
資産運用のヒントになる点があれば参考にしてみてください。
クレカ積立はマネックス証券!還元率1.1%(主要ネット証券で最大)

私の 運用方針 は【長期・分散・積立】が基本スタイルです。
そして、積立投資で活用しているのがクレカ積立!
積立の決済に対してポイントが付与されるのが魅力です。
このサービスで注目は マネックス証券![]() 。
。
マネックスカードで決済すれば、投信つみたての還元率1.1%!
主要ネット証券でNO.1の水準です。
毎月5万円の積立した場合、年間で6,600円分のポイントが貰える計算になります。
仮に20年間の積立投資を継続すれば、累計13万円以上のポイントが貯まることになります。
どうせ積立投資をするならば、利用した方がお得ですね。

※マネックスカードは、証券口座のオンライン上で申込する方式。
※カード積立を希望する人は、最初に口座開設を行ってください。
★マネックス証券は米国株投資でもメリットが大きい
米国株で時間外取引が可能な貴重な証券会社!
また、逆指値(リスクヘッジ)をしながら上値を追う戦略は私の鉄板手法です。